[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
養育費
【探偵無料相談所】賢く探偵社・興信所を選び・見積がとれる。
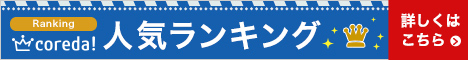

養育費とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用の事である。
[概要]
養育費は基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを子供を養育しない他方の親が支払う物である。養育費は結婚をしているか否かに関わらず請求する事ができ、また父親が子供を養育し、父親より母親の方が収入が多い場合、母親に請求することもできる。また養育費は裁判所を通さなくても、請求することが出来る。
[支給期間]
養育費の支給期間は法律で決められている訳ではないので、当事者との話し合いによって決められるが、話が纏まらない場合は、家庭裁判所に判断をゆだねる事もできる。基本的に日本国憲法で定めている成人とみなされる年齢20歳まで養育費を支払う例が多い。(外国の場合は外国の法律で成人とみなされる年齢まで)ただ、最近の傾向としては、当事者との約束で22歳まで支払われる例が多くなってきている。
[金額]
養育費の金額は親の生活水準によって異なり、民法752条生活保持義務により子どもは、生活水準が高い方の親と同水準の生活を求めることができる。家庭裁判所の調停によって決められた養育費の額は、子供一人につき月額2~4万円のケースが多い。これは、受給者が正確な養育費を事前に算出できない為、妥協してしまう事が多いからである。なお、一世帯の平均支給額は月額53,200円である。
養育費の金額は生活保護基準方式に基づき算出される。これは養育費は生活保護義務に当たるためである。金額は生活保護基準により左右されるが、ほぼ毎年基準が変わるため常に一定の金額ではない。
養育費とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用の事である。
[概要]
養育費は基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを子供を養育しない他方の親が支払う物である。養育費は結婚をしているか否かに関わらず請求する事ができ、また父親が子供を養育し、父親より母親の方が収入が多い場合、母親に請求することもできる。また養育費は裁判所を通さなくても、請求することが出来る。
[支給期間]
養育費の支給期間は法律で決められている訳ではないので、当事者との話し合いによって決められるが、話が纏まらない場合は、家庭裁判所に判断をゆだねる事もできる。基本的に日本国憲法で定めている成人とみなされる年齢20歳まで養育費を支払う例が多い。(外国の場合は外国の法律で成人とみなされる年齢まで)ただ、最近の傾向としては、当事者との約束で22歳まで支払われる例が多くなってきている。
[金額]
養育費の金額は親の生活水準によって異なり、民法752条生活保持義務により子どもは、生活水準が高い方の親と同水準の生活を求めることができる。家庭裁判所の調停によって決められた養育費の額は、子供一人につき月額2~4万円のケースが多い。これは、受給者が正確な養育費を事前に算出できない為、妥協してしまう事が多いからである。なお、一世帯の平均支給額は月額53,200円である。
養育費の金額は生活保護基準方式に基づき算出される。これは養育費は生活保護義務に当たるためである。金額は生活保護基準により左右されるが、ほぼ毎年基準が変わるため常に一定の金額ではない。
PR
親権
調査実績35年 原一探偵事務所

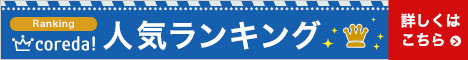

親権(しんけん)とは、一般的に、「子」を持つ「親」に対して法的に与えられている社会的かつ経済的な権利及び義務の総称のこと。日本国の民法を主眼に置いて言えば、その子を監護・教育する権利及び義務(監護教育権)、その子の居住場所を指定(確保)する権利及び義務(居住指定権)、子の財産管理をする権利及び義務(財産管理権)、及び、子の法定代理人たる地位にあって子のために法律行為などを行うための権利及び義務(法定代理権)などが「親権」として「親権を行う者」に与えられている。「親権を行う者」(民法、児童虐待防止法)を、「親権者」(民法)又は「保護者」(児童虐待防止法、学校教育法、精神保健福祉法)と呼ぶ。「親権者」は、必ずしもその「子」の「親」というわけではなく、「親」に虐待的な言動や離婚などがあった場合には、「親権」が移動したり、「親権」が分割される。「親権」が分割される場合、子の法定代理権を有する者を指して「親権者」と呼ぶことが多い。「親権者(保護者)」は、「親権を行う者」である限り「親権者(保護者)」であるのに対し、「子」は、「成年(現行の日本国では20歳の誕生日)」に達した時点で「親権者(保護者)」の「親権」による言動に服さなければならない法的義務から解放される。
親権(しんけん)とは、一般的に、「子」を持つ「親」に対して法的に与えられている社会的かつ経済的な権利及び義務の総称のこと。日本国の民法を主眼に置いて言えば、その子を監護・教育する権利及び義務(監護教育権)、その子の居住場所を指定(確保)する権利及び義務(居住指定権)、子の財産管理をする権利及び義務(財産管理権)、及び、子の法定代理人たる地位にあって子のために法律行為などを行うための権利及び義務(法定代理権)などが「親権」として「親権を行う者」に与えられている。「親権を行う者」(民法、児童虐待防止法)を、「親権者」(民法)又は「保護者」(児童虐待防止法、学校教育法、精神保健福祉法)と呼ぶ。「親権者」は、必ずしもその「子」の「親」というわけではなく、「親」に虐待的な言動や離婚などがあった場合には、「親権」が移動したり、「親権」が分割される。「親権」が分割される場合、子の法定代理権を有する者を指して「親権者」と呼ぶことが多い。「親権者(保護者)」は、「親権を行う者」である限り「親権者(保護者)」であるのに対し、「子」は、「成年(現行の日本国では20歳の誕生日)」に達した時点で「親権者(保護者)」の「親権」による言動に服さなければならない法的義務から解放される。
家庭裁判所
トラブル、お悩み解決【総合調査】 
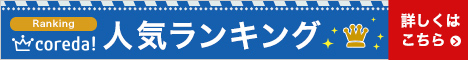

家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)とは、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する裁判所である(裁判所法31条の3第1項)。平成16年4月1日からは、人事訴訟(離婚訴訟など)及びこれに関する保全事件等も地方裁判所から移管され、これらを管轄している。改名の許可・不許可も家庭裁判所の管轄である。
家庭裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市、旭川市及び釧路市の合計50市に本庁が設けられているほか、支部及び出張所(同法31条の5、31条)も設けられている。
各家庭裁判所には、家庭裁判所調査官が置かれ(同法61条の2第1項)、人間科学に関する専門的知見を活用して、家事審判、家事調停及び少年審判に必要な調査や環境調整などの事務を行っている(同条2項)。
また、裁判は通常公正を期すために公開されるが、家庭裁判所は離婚などの人事訴訟や福祉犯罪に関する刑事事件などの訴訟事件を除き、当事者のプライバシーに配慮して原則非公開である。
家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)とは、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する裁判所である(裁判所法31条の3第1項)。平成16年4月1日からは、人事訴訟(離婚訴訟など)及びこれに関する保全事件等も地方裁判所から移管され、これらを管轄している。改名の許可・不許可も家庭裁判所の管轄である。
家庭裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市、旭川市及び釧路市の合計50市に本庁が設けられているほか、支部及び出張所(同法31条の5、31条)も設けられている。
各家庭裁判所には、家庭裁判所調査官が置かれ(同法61条の2第1項)、人間科学に関する専門的知見を活用して、家事審判、家事調停及び少年審判に必要な調査や環境調整などの事務を行っている(同条2項)。
また、裁判は通常公正を期すために公開されるが、家庭裁判所は離婚などの人事訴訟や福祉犯罪に関する刑事事件などの訴訟事件を除き、当事者のプライバシーに配慮して原則非公開である。

 ┃
┃