[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
離婚届
たった10日で浮気の証拠を押さえる方法【もし、あなたが…私が提示する“ある方法”を必ず「実行する」そう約束していただけるなら素人が探偵に頼らずにたった10日で浮気の証拠を押さえることができますが…】
離婚届(りこんとどけ)は、正式には離婚届書(りこんとどけしょ)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。
手続き根拠としては戸籍法第76条~第77条の2に規定されている。
[手続き]
協議離婚、裁判離婚の場合とも届出は夫婦の本籍地または所在地(現住所)ですることができる(法第25条)が、夫婦の本籍地以外の役場でする際は、戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)を添付しなければならない。
[協議離婚]
法律婚をしていた夫婦が協議離婚する場合、夫婦両名の署名押印(離婚前に作成する書類であるので、印鑑は同一の氏のもの)をしなければならないほか、成年の証人2名による署名押印が必要となる。
夫婦の間に未成年の子がある場合、それぞれの子について、夫婦だった者のどちらの親権に服するかを記載しなければならない(法第76条第1号)。
[裁判離婚]
家庭裁判所の調停・審判・判決によって離婚する場合は、届出書のほかに調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければならない(法第77条による法第63条の準用)。届出は、これらの成立または確定の日から10日以内に行うものとされており、届出書に成立・確定の日を記載しなければならない。裁判離婚の場合、証人による届出書への署名押印は必要ない。
夫婦の間に未成年の子がある場合、親権者と定められた者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載しなければならない(法第77条第1項)。
[離婚後に称する氏]
婚姻に際して氏を改めた者については、離婚後に元の(多くは両親の)戸籍に戻るか、新しい戸籍が作られ、元の氏を名乗ることになる(民法第767条)が、離婚の日から3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届(通称「離婚の際に称していた氏を称する届」)」を提出することにより、婚姻中に名乗っていた氏を名乗りつづけることができる(法第77条の2)。
ただし、離婚後3ヶ月以内に届出をしなかったり、法77条の2の届出をした後に婚姻前の氏に戻したりしようとする場合は、法第107条に定める、家庭裁判所による氏の変更の許可を得なければならなくなる。
離婚届(りこんとどけ)は、正式には離婚届書(りこんとどけしょ)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。
手続き根拠としては戸籍法第76条~第77条の2に規定されている。
[手続き]
協議離婚、裁判離婚の場合とも届出は夫婦の本籍地または所在地(現住所)ですることができる(法第25条)が、夫婦の本籍地以外の役場でする際は、戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)を添付しなければならない。
[協議離婚]
法律婚をしていた夫婦が協議離婚する場合、夫婦両名の署名押印(離婚前に作成する書類であるので、印鑑は同一の氏のもの)をしなければならないほか、成年の証人2名による署名押印が必要となる。
夫婦の間に未成年の子がある場合、それぞれの子について、夫婦だった者のどちらの親権に服するかを記載しなければならない(法第76条第1号)。
[裁判離婚]
家庭裁判所の調停・審判・判決によって離婚する場合は、届出書のほかに調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければならない(法第77条による法第63条の準用)。届出は、これらの成立または確定の日から10日以内に行うものとされており、届出書に成立・確定の日を記載しなければならない。裁判離婚の場合、証人による届出書への署名押印は必要ない。
夫婦の間に未成年の子がある場合、親権者と定められた者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載しなければならない(法第77条第1項)。
[離婚後に称する氏]
婚姻に際して氏を改めた者については、離婚後に元の(多くは両親の)戸籍に戻るか、新しい戸籍が作られ、元の氏を名乗ることになる(民法第767条)が、離婚の日から3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届(通称「離婚の際に称していた氏を称する届」)」を提出することにより、婚姻中に名乗っていた氏を名乗りつづけることができる(法第77条の2)。
ただし、離婚後3ヶ月以内に届出をしなかったり、法77条の2の届出をした後に婚姻前の氏に戻したりしようとする場合は、法第107条に定める、家庭裁判所による氏の変更の許可を得なければならなくなる。
PR
養育費
【探偵無料相談所】賢く探偵社・興信所を選び・見積がとれる。
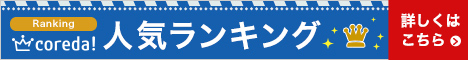

養育費とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用の事である。
[概要]
養育費は基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを子供を養育しない他方の親が支払う物である。養育費は結婚をしているか否かに関わらず請求する事ができ、また父親が子供を養育し、父親より母親の方が収入が多い場合、母親に請求することもできる。また養育費は裁判所を通さなくても、請求することが出来る。
[支給期間]
養育費の支給期間は法律で決められている訳ではないので、当事者との話し合いによって決められるが、話が纏まらない場合は、家庭裁判所に判断をゆだねる事もできる。基本的に日本国憲法で定めている成人とみなされる年齢20歳まで養育費を支払う例が多い。(外国の場合は外国の法律で成人とみなされる年齢まで)ただ、最近の傾向としては、当事者との約束で22歳まで支払われる例が多くなってきている。
[金額]
養育費の金額は親の生活水準によって異なり、民法752条生活保持義務により子どもは、生活水準が高い方の親と同水準の生活を求めることができる。家庭裁判所の調停によって決められた養育費の額は、子供一人につき月額2~4万円のケースが多い。これは、受給者が正確な養育費を事前に算出できない為、妥協してしまう事が多いからである。なお、一世帯の平均支給額は月額53,200円である。
養育費の金額は生活保護基準方式に基づき算出される。これは養育費は生活保護義務に当たるためである。金額は生活保護基準により左右されるが、ほぼ毎年基準が変わるため常に一定の金額ではない。
養育費とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用の事である。
[概要]
養育費は基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを子供を養育しない他方の親が支払う物である。養育費は結婚をしているか否かに関わらず請求する事ができ、また父親が子供を養育し、父親より母親の方が収入が多い場合、母親に請求することもできる。また養育費は裁判所を通さなくても、請求することが出来る。
[支給期間]
養育費の支給期間は法律で決められている訳ではないので、当事者との話し合いによって決められるが、話が纏まらない場合は、家庭裁判所に判断をゆだねる事もできる。基本的に日本国憲法で定めている成人とみなされる年齢20歳まで養育費を支払う例が多い。(外国の場合は外国の法律で成人とみなされる年齢まで)ただ、最近の傾向としては、当事者との約束で22歳まで支払われる例が多くなってきている。
[金額]
養育費の金額は親の生活水準によって異なり、民法752条生活保持義務により子どもは、生活水準が高い方の親と同水準の生活を求めることができる。家庭裁判所の調停によって決められた養育費の額は、子供一人につき月額2~4万円のケースが多い。これは、受給者が正確な養育費を事前に算出できない為、妥協してしまう事が多いからである。なお、一世帯の平均支給額は月額53,200円である。
養育費の金額は生活保護基準方式に基づき算出される。これは養育費は生活保護義務に当たるためである。金額は生活保護基準により左右されるが、ほぼ毎年基準が変わるため常に一定の金額ではない。
弁護士
~幸せと証拠を掴む浮気調査~RMC(REAL MIND CONVICTION【彼の本音を知る方法】
弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得る。 日本では、その職掌・資格に関しては弁護士法などで規定されている。シンボルは中央にエジプト神話マアトの「真実の羽根」との重さを比較する天秤を配した向日葵(ひまわり)で、徽章(バッジ)もこのデザインによる。
一般民事とは、主として個人から依頼される民事上の一般的な法律問題を扱う分野である。一般民事はさらに、過払金返還、保険金請求(被害者側)、示談交渉、個人の破産・再生などがある。
一般民事を取り扱う弁護士が扱うことの多い分野としては、他には、家事、消費者問題(消費者側)や労働問題(労働者側)、一般企業法務などもある。
家事とは、離婚や相続など、家事事件に関する法律問題を扱うものである。しばしば渉外案件(外国人の離婚や相続など)となる。
消費者問題は、消費者と企業の間の紛争を取り扱うものである。
労働問題は、労働者と使用者の間の紛争を取り扱うものである。
一般企業法務は、後述する企業法務に属する。
企業法務(広義)とは、主として企業を依頼とする法律問題を扱う分野である。企業法務(広義)は、多くの場合、狭義の企業法務(コーポレートとも。)、金融法務(ファイナンスとも)、税務、知的財産、倒産・事業再生、紛争処理などの分野に分かれている。いずれの分野も渉外案件を含み得る。狭義の企業法務には、一般企業法務(ジェネラル・コーポレートとも)、ガバナンス、M&A、労働問題(使用者側)などが含まれる。金融法務は、銀行、証券、保険、金融規制、ストラクチャード・ファイナンス、アセット・マネジメントなどを扱うものである。
刑事とは、主として被疑者や被告人の弁護を扱う分野である。公判における法廷活動だけでなく、不起訴に向けた活動、示談交渉や保釈請求、勾留中の被疑者・被告人と外部との連絡役なども含まれる。
その他のカテゴリーとしては、行政事件や人権に関わる事件などがあると思われる。しかし、依頼主によって一般民事ないし企業法務との位置づけも可能である。(もっとも、公共団体等からの依頼であれば、一般民事でも企業法務でもない分野とはいえよう)結局のところ、各分野は相互に重なり合う部分があり、その区別は基本的に相対的なものである。
弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得る。 日本では、その職掌・資格に関しては弁護士法などで規定されている。シンボルは中央にエジプト神話マアトの「真実の羽根」との重さを比較する天秤を配した向日葵(ひまわり)で、徽章(バッジ)もこのデザインによる。
一般民事とは、主として個人から依頼される民事上の一般的な法律問題を扱う分野である。一般民事はさらに、過払金返還、保険金請求(被害者側)、示談交渉、個人の破産・再生などがある。
一般民事を取り扱う弁護士が扱うことの多い分野としては、他には、家事、消費者問題(消費者側)や労働問題(労働者側)、一般企業法務などもある。
家事とは、離婚や相続など、家事事件に関する法律問題を扱うものである。しばしば渉外案件(外国人の離婚や相続など)となる。
消費者問題は、消費者と企業の間の紛争を取り扱うものである。
労働問題は、労働者と使用者の間の紛争を取り扱うものである。
一般企業法務は、後述する企業法務に属する。
企業法務(広義)とは、主として企業を依頼とする法律問題を扱う分野である。企業法務(広義)は、多くの場合、狭義の企業法務(コーポレートとも。)、金融法務(ファイナンスとも)、税務、知的財産、倒産・事業再生、紛争処理などの分野に分かれている。いずれの分野も渉外案件を含み得る。狭義の企業法務には、一般企業法務(ジェネラル・コーポレートとも)、ガバナンス、M&A、労働問題(使用者側)などが含まれる。金融法務は、銀行、証券、保険、金融規制、ストラクチャード・ファイナンス、アセット・マネジメントなどを扱うものである。
刑事とは、主として被疑者や被告人の弁護を扱う分野である。公判における法廷活動だけでなく、不起訴に向けた活動、示談交渉や保釈請求、勾留中の被疑者・被告人と外部との連絡役なども含まれる。
その他のカテゴリーとしては、行政事件や人権に関わる事件などがあると思われる。しかし、依頼主によって一般民事ないし企業法務との位置づけも可能である。(もっとも、公共団体等からの依頼であれば、一般民事でも企業法務でもない分野とはいえよう)結局のところ、各分野は相互に重なり合う部分があり、その区別は基本的に相対的なものである。

 ┃
┃