[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
形式的意義における民法(民法典)
調査実績35年 原一探偵事務所

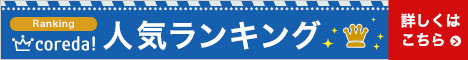

形式的意義における民法とは、制定法である「民法」という名の法律、いわゆる民法典のことをいう。具体的には、明治29年法律第89号により定められた民法第一編第二編第三編(総則、物権、債権)及び明治31年法律第9号により定められた民法第四編第五編(親族、相続)が民法典である(両者の関係については後述)。全体が1898年7月16日から施行された。その後、日本国憲法の制定に伴い、その精神に適合するように(特に家制度の廃止など)後2編を中心に根本的に改正された。
以上のように、民法典は、形式上は明治29年の法律と明治31年の法律の二つの法律から構成されると理解されることが多く、市販の六法全書なども両者を別の法典を構成するものとして扱うことが多かった。これに対し、法制執務上は、後者は前者に条文を加える旨の改正法であり、民法典は形式上も一つの法典であるとする立場が採用されていた(例えば、民法第四編又は第五編の条文を引用する際にも「民法(明治29年法律第89号)」として引用される。ただし、例外的に(誤って?)「民法(明治31年法律第9号)」として引用される例がないわけではない)。
この点については、口語化と保証制度の見直しを主な目的とした民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)が2005年に施行されたことに伴い民法の目次の入換えがされ、入換後の目次が一体となっていることから、今後は一つの法典として理解することになるとの理解も唱えられている。
制定当時の民法と現在の民法は形式上は同じ法律であるが、家族法についてはその内容に大きな変化が加えられているため、戦後の改正以前の民法(特に家族法)を「明治民法」と称することもある。
形式的意義における民法とは、制定法である「民法」という名の法律、いわゆる民法典のことをいう。具体的には、明治29年法律第89号により定められた民法第一編第二編第三編(総則、物権、債権)及び明治31年法律第9号により定められた民法第四編第五編(親族、相続)が民法典である(両者の関係については後述)。全体が1898年7月16日から施行された。その後、日本国憲法の制定に伴い、その精神に適合するように(特に家制度の廃止など)後2編を中心に根本的に改正された。
以上のように、民法典は、形式上は明治29年の法律と明治31年の法律の二つの法律から構成されると理解されることが多く、市販の六法全書なども両者を別の法典を構成するものとして扱うことが多かった。これに対し、法制執務上は、後者は前者に条文を加える旨の改正法であり、民法典は形式上も一つの法典であるとする立場が採用されていた(例えば、民法第四編又は第五編の条文を引用する際にも「民法(明治29年法律第89号)」として引用される。ただし、例外的に(誤って?)「民法(明治31年法律第9号)」として引用される例がないわけではない)。
この点については、口語化と保証制度の見直しを主な目的とした民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)が2005年に施行されたことに伴い民法の目次の入換えがされ、入換後の目次が一体となっていることから、今後は一つの法典として理解することになるとの理解も唱えられている。
制定当時の民法と現在の民法は形式上は同じ法律であるが、家族法についてはその内容に大きな変化が加えられているため、戦後の改正以前の民法(特に家族法)を「明治民法」と称することもある。
PR
実質的意義における民法
有利な離婚!平均の2倍の養育費を受け取る方法!
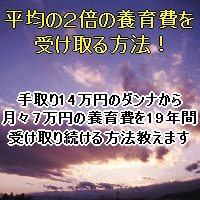
民法典の中に若干異質な規定(例えば84条の3・1005条のような罰則規定)があること、および、民法典以外にも民法典中の規定と等質ないし極めて近接した性格の事柄を規律対象とする法規範が存在することから、このような概念が立てられる。
この場合、「市民生活における市民相互の関係(財産関係、家族関係)を規律する法」として、民法典の諸規定に加え、不動産登記法・戸籍法などの諸法もここでいう「民法」に含まれるものとされる。
ただし、いかなる特別法がこの「民法」に含まれるのか、必ずしも明確な基準があるわけではなく、学者によりその説く範囲は異なっている。そのため、この概念区分の実益に疑問が呈されることもある。
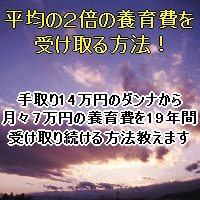
民法典の中に若干異質な規定(例えば84条の3・1005条のような罰則規定)があること、および、民法典以外にも民法典中の規定と等質ないし極めて近接した性格の事柄を規律対象とする法規範が存在することから、このような概念が立てられる。
この場合、「市民生活における市民相互の関係(財産関係、家族関係)を規律する法」として、民法典の諸規定に加え、不動産登記法・戸籍法などの諸法もここでいう「民法」に含まれるものとされる。
ただし、いかなる特別法がこの「民法」に含まれるのか、必ずしも明確な基準があるわけではなく、学者によりその説く範囲は異なっている。そのため、この概念区分の実益に疑問が呈されることもある。
日本の民法と各国の民法の関係
~幸せと証拠を掴む浮気調査~RMC(REAL MIND CONVICTION【彼の本音を知る方法】
日本における現行の民法典は、1898年(明治31年)に施行された「民法(明治29年法律第89号)」である。1890年(明治23年)に公布された、いわゆる旧民法が、フランス民法(いわゆるナポレオン民法典)を範としていたのに対し、現在の日本民法典は、ドイツ民法を手本にしたとされていた。これを、単に継受、あるいは法典継受という。もっとも、この時参照されたのは、制定されたドイツ民法そのものではなくドイツ民法草案である(ドイツ民法は、1896年に公布され、1900年に施行された。)。これに加え、大正期以後、日本法学がドイツの多大なる影響下に発展したことを受けてドイツ民法の日本法に与える影響ははかり知れない(これを、法典継受との対比において学説継受ということもある)。戦前の民法学の大家であった鳩山秀夫らがドイツ民法の大きな影響を受けていたことや、日本民法学において長年にわたり第一人者であった我妻栄がドイツ民法的な思考方法で戦後日本民法の理論を構築したこともあって、現在の判例理論上のドイツ民法的な思考方法が多く見られる。
ところが、近年になり、日本民法は、その構成についてはドイツ民法典の構成に準じた構成がされているが、その内容についてはむしろフランス民法をベースとして構築されていると主張されるようになり、学界にあってはこの観点からの民法理論の再構築がおこなわれている。これは、旧民法がフランス民法を継受したものであったことのほか、民法典の起草を担当した三博士のうち、梅謙次郎と富井政章の二人の留学先がフランスであったという事情による。この流れを牽引したのは星野英一や平井宜雄である。もっとも、起草にあたってはドイツ民法草案第一が最も頻繁に参照されたこと、穂積は、イギリス留学の途中、依願により民法学論争たけなわであったドイツに留学先を変更し、梅もドイツに一年程度留学していたこと、起草補助委員の一人、仁井田益太郎が当時日本に数少ないドイツ法の専門であったこと、富井にいたってはドイツ留学経験がないにも関わらず梅・穂積以上にドイツ法を重視していたこと等に留意する必要がある。この点から星野らに反論するのは加藤雅信である。
なお、日本民法はイギリス民法からも若干の影響を受けている。特に、ウルトラ・ヴィーレスの法理を規定した民法43条(法人の能力)や、Hadley v. Baxendale事件の判決で表明されたルールを継受した民法416条(損害賠償の範囲)のほか、民法526条(隔地者間の契約の成立時期)がそれにあたるとされる。起草者の穂積陳重が、当初イギリスに留学したことの影響とされている。
その他、仁井田らにより民法の起草趣旨が記録された「民法修正案理由書」によれば、フランス・ドイツ・イギリス法はもとより、スイス・オーストリア・ベルギー・インド・イタリア・スペイン・ポルトガル・オランダ・ギリシャ・アメリカ・カナダ・ロシア・モンテネグロ・さらには日本の中世法に至るまで、膨大な法典・草案が参照されたことが明記されている。
以上のことから、日本民法は、特定の母法のみに基づくというよりも、多角的に比較法の参照が行われて立案されたと評価されている。
日本における現行の民法典は、1898年(明治31年)に施行された「民法(明治29年法律第89号)」である。1890年(明治23年)に公布された、いわゆる旧民法が、フランス民法(いわゆるナポレオン民法典)を範としていたのに対し、現在の日本民法典は、ドイツ民法を手本にしたとされていた。これを、単に継受、あるいは法典継受という。もっとも、この時参照されたのは、制定されたドイツ民法そのものではなくドイツ民法草案である(ドイツ民法は、1896年に公布され、1900年に施行された。)。これに加え、大正期以後、日本法学がドイツの多大なる影響下に発展したことを受けてドイツ民法の日本法に与える影響ははかり知れない(これを、法典継受との対比において学説継受ということもある)。戦前の民法学の大家であった鳩山秀夫らがドイツ民法の大きな影響を受けていたことや、日本民法学において長年にわたり第一人者であった我妻栄がドイツ民法的な思考方法で戦後日本民法の理論を構築したこともあって、現在の判例理論上のドイツ民法的な思考方法が多く見られる。
ところが、近年になり、日本民法は、その構成についてはドイツ民法典の構成に準じた構成がされているが、その内容についてはむしろフランス民法をベースとして構築されていると主張されるようになり、学界にあってはこの観点からの民法理論の再構築がおこなわれている。これは、旧民法がフランス民法を継受したものであったことのほか、民法典の起草を担当した三博士のうち、梅謙次郎と富井政章の二人の留学先がフランスであったという事情による。この流れを牽引したのは星野英一や平井宜雄である。もっとも、起草にあたってはドイツ民法草案第一が最も頻繁に参照されたこと、穂積は、イギリス留学の途中、依願により民法学論争たけなわであったドイツに留学先を変更し、梅もドイツに一年程度留学していたこと、起草補助委員の一人、仁井田益太郎が当時日本に数少ないドイツ法の専門であったこと、富井にいたってはドイツ留学経験がないにも関わらず梅・穂積以上にドイツ法を重視していたこと等に留意する必要がある。この点から星野らに反論するのは加藤雅信である。
なお、日本民法はイギリス民法からも若干の影響を受けている。特に、ウルトラ・ヴィーレスの法理を規定した民法43条(法人の能力)や、Hadley v. Baxendale事件の判決で表明されたルールを継受した民法416条(損害賠償の範囲)のほか、民法526条(隔地者間の契約の成立時期)がそれにあたるとされる。起草者の穂積陳重が、当初イギリスに留学したことの影響とされている。
その他、仁井田らにより民法の起草趣旨が記録された「民法修正案理由書」によれば、フランス・ドイツ・イギリス法はもとより、スイス・オーストリア・ベルギー・インド・イタリア・スペイン・ポルトガル・オランダ・ギリシャ・アメリカ・カナダ・ロシア・モンテネグロ・さらには日本の中世法に至るまで、膨大な法典・草案が参照されたことが明記されている。
以上のことから、日本民法は、特定の母法のみに基づくというよりも、多角的に比較法の参照が行われて立案されたと評価されている。

 ┃
┃