[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
離婚が子供に与える影響
有利な離婚!平均の2倍の養育費を受け取る方法!
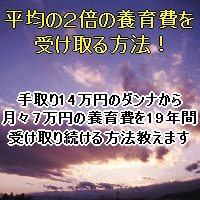
かつて、離婚は子供に何の影響も与えないと考えられていた。アメリカの心理学者ジュディス・ウォーラースタインは、親が離婚した子供を長期に追跡調査して、子供達は大きな精神的な打撃を受けていることを見出した。子供達は、両方の親から見捨てられる不安を持ち、学業成績が悪く、成人してからの社会的地位も低く、自分の結婚も失敗に終わりやすいなどの影響があった。ウォーラースタインの結果について、多くの国で大規模な追跡調査が行われ、悪影響が実際に存在することが確認された。
日本も批准した子どもの権利条約では、その対策として、(1)子供の処遇を決めるに際しては、年齢に応じて子供の意見を聞くこと、(2)別居が始まれば子殿も福祉に障害が生じない限り両親との接触を維持することを求めている。
離婚の悪影響を少なく抑えるための条件は、二人の親の間で争いが少なく、近くに住んで、再婚せず、二親とも育児に関わり、育児時間が50%ずつに近いことであるとの主張が父権を主張するがわから指摘されている。実際には居住地を片親の要求で定期的に変えなければならないことを子供が嫌がるなど二世帯で子供を共有させることには無理があるのではないかとの主張もある。実際に上記の調査結果に対しても、子の育成の問題は離婚後の経済環境にあり、必ずしも父親との関係が薄れることではないとの調査結果も存在する。
また各国で、子供から引き離された片親が片親引き離し症候群(PAS)にかかるとの報告も存在する。
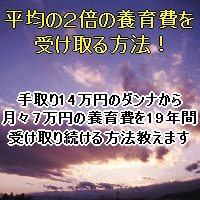
かつて、離婚は子供に何の影響も与えないと考えられていた。アメリカの心理学者ジュディス・ウォーラースタインは、親が離婚した子供を長期に追跡調査して、子供達は大きな精神的な打撃を受けていることを見出した。子供達は、両方の親から見捨てられる不安を持ち、学業成績が悪く、成人してからの社会的地位も低く、自分の結婚も失敗に終わりやすいなどの影響があった。ウォーラースタインの結果について、多くの国で大規模な追跡調査が行われ、悪影響が実際に存在することが確認された。
日本も批准した子どもの権利条約では、その対策として、(1)子供の処遇を決めるに際しては、年齢に応じて子供の意見を聞くこと、(2)別居が始まれば子殿も福祉に障害が生じない限り両親との接触を維持することを求めている。
離婚の悪影響を少なく抑えるための条件は、二人の親の間で争いが少なく、近くに住んで、再婚せず、二親とも育児に関わり、育児時間が50%ずつに近いことであるとの主張が父権を主張するがわから指摘されている。実際には居住地を片親の要求で定期的に変えなければならないことを子供が嫌がるなど二世帯で子供を共有させることには無理があるのではないかとの主張もある。実際に上記の調査結果に対しても、子の育成の問題は離婚後の経済環境にあり、必ずしも父親との関係が薄れることではないとの調査結果も存在する。
また各国で、子供から引き離された片親が片親引き離し症候群(PAS)にかかるとの報告も存在する。
PR
離婚の原因
15,000人が実証済み!あらゆる離婚問題を完全解決!次はあなたの悩みを解決する番です。
【満足度96.4%!】どんな離婚問題もスピード解決!澁川良幸が贈る「15,000人の離婚問題解決法」~あなたの離婚問題もきっと解決できます~

司法統計によれば、離婚の申し立てにおいて、夫からの申し立て理由は「性格が合わない」、「異性関係」、「異常性格」の順で多い。また妻からの申し立て理由は、「性格が合わない」、「暴力をふるう」、「異性関係」の順で多い。
アメリカでは、大学の公開講座や宗教団体などが、健全な家庭生活を維持・増進させるための活動をしているが、そうした団体の一つであるThe National Marriage Project は、離婚の原因は「家庭の運営に必要な知識を持っていないこと」であるとして、必要な情報を提供している。また、Marriage Builders (ウィラード・ハーリ)は、「心からの合意の原則」など、考え方の食い違いを調整するための概念について解説している。また、Smart Marriage では、離婚の原因は「意見の食い違いを調整する技術を持たないこと」であるとして、その技術を習得するための教育を行い成果を挙げている。また、アメリカ合衆国政府は、米国厚生省の「健全な家庭生活への新しい方法」や、「国立健全な結婚情報センター」の結婚教育などにより、交渉の仕方やコミュニケーション能力や、対立の解決の仕方について情報提供を行っている。
【満足度96.4%!】どんな離婚問題もスピード解決!澁川良幸が贈る「15,000人の離婚問題解決法」~あなたの離婚問題もきっと解決できます~

司法統計によれば、離婚の申し立てにおいて、夫からの申し立て理由は「性格が合わない」、「異性関係」、「異常性格」の順で多い。また妻からの申し立て理由は、「性格が合わない」、「暴力をふるう」、「異性関係」の順で多い。
アメリカでは、大学の公開講座や宗教団体などが、健全な家庭生活を維持・増進させるための活動をしているが、そうした団体の一つであるThe National Marriage Project は、離婚の原因は「家庭の運営に必要な知識を持っていないこと」であるとして、必要な情報を提供している。また、Marriage Builders (ウィラード・ハーリ)は、「心からの合意の原則」など、考え方の食い違いを調整するための概念について解説している。また、Smart Marriage では、離婚の原因は「意見の食い違いを調整する技術を持たないこと」であるとして、その技術を習得するための教育を行い成果を挙げている。また、アメリカ合衆国政府は、米国厚生省の「健全な家庭生活への新しい方法」や、「国立健全な結婚情報センター」の結婚教育などにより、交渉の仕方やコミュニケーション能力や、対立の解決の仕方について情報提供を行っている。
離婚件数・率
離婚大全集~圧倒的有利に離婚する方法~

「人口千人あたりの、一年間の離婚件数」(「人口千人あたりの、生涯のどこかで離婚する人数」とは異なる)のことを普通離婚率というが、これは人口の年齢構成の影響を強く受ける。これ以外の離婚率を特殊離婚率という。特殊離婚率には、例えば男女別年齢別有配偶離婚率や、結婚経過年数別離婚率などがある。
マスコミなどで言われる「3組に1組が離婚」などの表現は、全国のその年のみの離婚件数を全国のその年のみの新規婚姻件数で割った指標に基づくものであり、これは厚生労働省が定義する「離婚率」とは異なる。 これは、近年大きな変動のない婚姻件数のうち、生涯のどこかで離婚する割合を暗示するデータとして用いられているが、今年離婚した者が結婚した年の婚姻件数が、今年の婚姻件数と一致するわけではないので、結婚した組のうち生涯のどこかでどのくらいが離婚したかを正確に表しているとは言えない。
日本では、普通離婚率は1883年(明治16年)には3.38であったが、大正・昭和期にかけて低下し、1935年には0.70となった。その後1950年前後(約1)および1984年(1.51)に二度の山を形成したが、1990年代から再び上昇し、2002年には2.30を記録した。
日本では平成元年から平成15年にかけて離婚件数が増加し、その後減少している。厚生労働省「人口動態統計」によると、平成14年の離婚件数は約29万件、平成18年は約25万件となっている(離婚率でいえば、平成17年で人口1000人あたり2.08である)。平成14年を境に減少傾向となっており、離婚率が3.39であった明治時代に比べれば少ない(これは、明治時代の女性は処女性よりも労働力として評価されており、再婚についての違和感がほとんどなく、嫁の追い出し・逃げ出し離婚も多かったこと、離婚することを恥とも残念とも思わない人が多かったことが理由とされている)。現代の離婚の原因の主なものは「性格の不一致」である。また、熟年結婚が熟年夫婦による離婚の数値を押し上げている。

「人口千人あたりの、一年間の離婚件数」(「人口千人あたりの、生涯のどこかで離婚する人数」とは異なる)のことを普通離婚率というが、これは人口の年齢構成の影響を強く受ける。これ以外の離婚率を特殊離婚率という。特殊離婚率には、例えば男女別年齢別有配偶離婚率や、結婚経過年数別離婚率などがある。
マスコミなどで言われる「3組に1組が離婚」などの表現は、全国のその年のみの離婚件数を全国のその年のみの新規婚姻件数で割った指標に基づくものであり、これは厚生労働省が定義する「離婚率」とは異なる。 これは、近年大きな変動のない婚姻件数のうち、生涯のどこかで離婚する割合を暗示するデータとして用いられているが、今年離婚した者が結婚した年の婚姻件数が、今年の婚姻件数と一致するわけではないので、結婚した組のうち生涯のどこかでどのくらいが離婚したかを正確に表しているとは言えない。
日本では、普通離婚率は1883年(明治16年)には3.38であったが、大正・昭和期にかけて低下し、1935年には0.70となった。その後1950年前後(約1)および1984年(1.51)に二度の山を形成したが、1990年代から再び上昇し、2002年には2.30を記録した。
日本では平成元年から平成15年にかけて離婚件数が増加し、その後減少している。厚生労働省「人口動態統計」によると、平成14年の離婚件数は約29万件、平成18年は約25万件となっている(離婚率でいえば、平成17年で人口1000人あたり2.08である)。平成14年を境に減少傾向となっており、離婚率が3.39であった明治時代に比べれば少ない(これは、明治時代の女性は処女性よりも労働力として評価されており、再婚についての違和感がほとんどなく、嫁の追い出し・逃げ出し離婚も多かったこと、離婚することを恥とも残念とも思わない人が多かったことが理由とされている)。現代の離婚の原因の主なものは「性格の不一致」である。また、熟年結婚が熟年夫婦による離婚の数値を押し上げている。

 ┃
┃